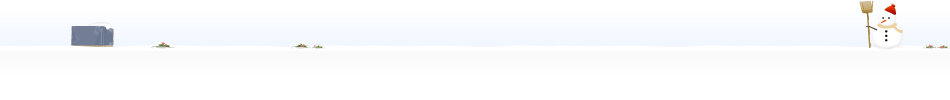健康食品、化粧品、はちみつ・自然食品の山田養蜂場。「ひとりの人の健康」のために大切な自然からの贈り物をお届けいたします。
健康食品、化粧品、はちみつ・自然食品の山田養蜂場。「ひとりの人の健康」のために大切な自然からの贈り物をお届けいたします。
大通りに面した、小さな古い家に、かすみさんは、レモンカナリアと住んでいます。
もうすぐ六十才になるのですが、若いころからひざが悪くて、あまり外へ出られないので、一日中すわって、仕事をしています。
それは、デパートやお店からたのまれて、洋服やエプロン、いろいろなカバーなどにししゅうをすることです。
かすみさんのししゅうは、とても評判がよくて、注文がとぎれることはありませんでした。
今にも口に入れたくなるような、つやつやとしたさくらんぼや、さきたてのいいにおいがしそうなバラの花のししゅうに、お客さんはもちろん、店の人も、
「ほう。みごとなものですねえ。」と、うなるほどでした。
近ごろは、老眼鏡がいるようになりましたが、そのあざやかな仕事ぶりは、かわることがありませんでした。
今日も、まどべのお気に入りのいすにこしかけ、大きな銀ぶちの老眼鏡をキラキラさせてししゅうをしていると、玄関のチャイムがなりました。
いつものデパートの店の人です。
かすみさんは、先月たのまれていたランチョンマットを三十枚、わたしました。
店の人は、一枚ずつ見ながら、
「この小鳥は本物そっくりですね。ちょっとずつ、みんな表情がちがうのもいいなあ。」
と、目を見張りました。
「うちのカナリアをモデルにしたのですよ。」
「上出来ですね。ところで、今日はちょっとかわった注文があるのですが。」
かすみさんは、老眼鏡をはずしながら、
「それは、どんな注文でしょう。」
と、たずねました。
「テーブルクロスの注文なんですがね、紅茶が飲みたくなるようなししゅうをしてほしいとたのまれたんですよ。デザインは、おまかせすると。」
店の人は、困った様子で言いました。
「紅茶が飲みたくなるテーブルクロス?それはまた、どういう方がたのまれたのですか。」
かすみさんは、思わずたずねてしまいました。
「はい。もうすぐ結婚する方で、結婚の記念にしたいそうです。」
長いこと、ししゅうの仕事をしてきましたが、こういう注文は初めてでした。いつも、決まったデザインやイニシャルを入れることが多く、デザインをまかせるなんて、めったにありません。
でも、まかせてもらえるというのは、逆に自由に考えることができるということです。
(何だかおもしろそうね。)
かすみさんは、自分でもびっくりするような大きな声で、
「やってみます。」
と、答えていました。
「そう言ってもらえると思っていたんですよ。いやあ、よかった、よかった。では、二ヶ月後にうかがいますね。」
店の人は、とたんにはずんだ声にかわると、代わりにずっしりと重いつつみを置いて、帰って行きました。
つつみをあけてみると、中から真っ白なテーブルクロスがでてきました。広げてみるとずいぶん、大きなものです。
「まあ、これは、上等な麻じゃないの。これだけの布にししゅうとなると、ちょっと大変ね。さて、紅茶の飲みたくなるテーブルクロスねえ…。」
かすみさんは、白い布を広げたまま、考え込んでしまいました。
「わたしだったら、どんなところで飲みたいかしら?そうねえ、山で小鳥のさえずりを聞きながらとか、あっそうそう、バラの花の咲く庭をながめながらとか、うーん、海のそばで潮の香りにつつまれてとか、いいわねえ。」
いろいろと思いうかべてみましたが、なかなか決まりません。
「ルル、どうしよう?」
かすみさんは、レモンカナリアのルルにきいてみましたが、ルルは目をキロキロさせただけです。
「だれかといっしょに飲みたいわねえ。友達とか、家族とか。
そうそう、子どものころ、近くの小川のそばでよく遊んだわね。お天気のいい日は、となりのおねえさんたちと、焼きたてのビスケットで紅茶を飲んだこともあったわ。川原には白つめ草がさいて、クローバーがびっしりとはえていて、緑のじゅうたんみたいだった。小川に入って水遊びをして、お気に入りのワンピースをぬ らしたんだっけ。」
かすみさんは、いっしょに行った、妹たちや、となりの家の、背の高いみかさんというお姉さんのことを思い出しました。木かげで昼寝をしたこと、お気に入りのギンガムチェックの赤いワンピースまで思い出したのです。
「楽しかったわねえ。そうだ、クローバーがいいわ。白つめ草がたくさん咲く、緑のじゅうたんをさしてみましょう。」
かすみさんは、さっそく仕事にとりかかりました。
お日さまに当たって、輝くような明るい緑色、こけのようにしっとりとした緑色。いろいろな種類の緑色のししゅう糸を使って、クローバーの葉を一まい、一まい、ていねいにさしていきました。それから、クリーム色の細いリボンを取り出すと、白つめ草をさしていきました。
一はりさすと、花びらが一まいふわり、また一さしすると、一まいふわりと、でき上がっていきます。かすみさんは、ワクワクしながら、ししゅうをしていきました。そうして、一輪でき上がった時、花がフルンと、ゆれたような気がしました。
どのくらいたったのでしょう。
あたりはすっかり夕ぐれでした。
「ああ、よくがんばったわね。今日は、何だか夢中で仕事をしたわ。」
シチューをあたためながら、かすみさんは楽しくて仕方ありませんでした。
一週間ほど過ぎた頃でしょうか。かすみさんは、テーブルクロスの上に、一ぴきのミツバチをみつけました。ミツバチは、しばらくクローバーの上をとんでから、白つめ草の上にとまったのです。
かすみさんは、追いはらおうと思ったのですが、しばらくすると、いなくなったので、そのままにしていました。
ところが、次の日から毎日、ミツバチがやってくるようになり、白つめ草にとまるのです。はじめはちょっとこわかったかすみさんでしたが、
「このミツバチ、本物の花とまちがえているんだわ。」
と、思うと、なんだかおかしくなりました。
不思議なことは、かすみさんがししゅうをしている時は、現れないことです。
そして、ミツバチの数は、花がふえるごとに多くなりました。
ある日、かすみさんの家に、一人の男の人がやって来ました。四十才くらいでしょうか。
ぼうしをかぶって、おそろいの茶色のベストにズボンという、かっこうです。日にやけた顔をニコニコさせて言いました。
「こんにちは。わたしは、はちやといいまして、ミツバチをかって、はちみつをとる仕事をしています。近頃、うちのハチたちが、クローバーのみつを集めてきましてね。どこにクローバーの畑があるのかと探していたら、ここに来たのです。」
「まあ、はちやさん?せっかくですが、うちには庭も畑もないんですよ。何かのまちがいでしょう。」
と、かすみさんが言うと、男の人は、「いや、たしかにここへ来ているのです。まちがいありません。」と言って、ゆずりません。
かすみさんは、ミツバチといえば、ししゅうしたテーブルクロスの上に、よく来ることを話しました。
「そのテーブルクロス、見せてもらえませんか?」
そこで、かすみさんはさっそく、部屋へ案内しました。
すると、何ということでしょう!
さっきまでししゅうをしていたテーブルクロスは、クローバーの小さな草原になって、風にそよいでいたのです。
「いい畑があるじゃないですか。この花といい、葉といい、なるほどこれなら、いいみつがとれるわけだ。」
そう言いながら、白つめ草にそっと、ふれました。すると、花はたしかに、フルンとゆれたのです。
「まあ、どうしたんでしょう。今動いたわ!ししゅうなのに…。」
かすみさんは、何度もめがねをはずしたりかけたりしながら、クローバーをそっとなでてみました。
「その、ミツバチが集めたみつなんですがね、これまた、特上のいいはちみつなんですよ。どうです?味をみてみませんか。」
はちやさんはあわてて、もってきたふくろから、小さなびんを取り出しました。その中には、金色に輝くはちみつが、ゆらりと入っていました。
「すばらしい味なんですよ。甘さといい、色といい、香りといい、これだけのはちみつはめったに手に入ることはありませんよ。ほら。」
かすみさんは、さし出されたスプーン一ぱいのはちみつを、おそるおそる口に入れてみました。
これがはちみつでしょうか。ふわっと広がる香りにつつまれると、まるでクローバーの畑の中にいるような気がしました。
その畑からよびもどすかのように、はちやさんは、小びんのふたをしめながら、しずかに言いました。
「今、あなたがなめた一さじのはちみつは、ミツバチ一ぴきが一生かかって集めたはちみつなのですよ。」
その言葉を聞いて、かすみさんは、ごくりとつばをのみこみました。
(一生はたらいて集めたはちみつ…。)
一ぴきのミツバチの命をもらったようで、かすみさんの心は、ズシンと重くなりました。
はちやさんは、かすみさんの顔をのぞきこむと、
「このはちみつ、まぼろしのはちみつとして売ってもいいですか。」
と、たずねました。
「ええ、 どうぞ。」
かすみさんが答えると、はちやさんは、
「近頃は、めっきり花畑が少なくなりましてね。いいはちみつがとれなくて、困っていたのです。これで、またがんばれますよ。」
そう言って、はちみつをとらせてもらうお礼にと、お金の入ったふうとうをさし出しました。
はちやさんが帰ったあと、かすみさんは、何度も首をかしげながら、
「本当にあのミツバチたち、みつをすっているのかしら?」
と、つぶやきました。
だって、小さな草原は、今はもう、ししゅうのテーブルクロスにもどっていたのですから。
次の日からまた、かすみさんは、針を持ち続けました。何しろ、大きなテーブルクロスでしたから、たくさんさしたつもりでも、ほんの少しです。夢中になってさしていると、本当に、クローバーの草原にすわりこんでいるような気がして、ハッと顔を上げるのでした。
「少し、疲れたのかしら?」
ししゅうのすきなかすみさんも、時々、かたが痛くなったり、目がショボショボしました。そんな時は、あのはちみつをたっぷり入れた紅茶を飲むと、体の疲れがすーっと、とれていくのでした。
おまけに、気持ちがシャンとなって、かすみさんは、 針を持つ手を休めることは、ありませんでした。
「何だかわたし、働きバチみたいね。」
かすみさんは、クスッと笑いました。
ところが、少し無理をしすぎたのでしょうか。
ある日、最後のはちみつを入れた紅茶を飲んでため息をついたとたん、頭がくらくらとして、テーブルクロスの上に、たおれこんでしまったのです。
そして、どのくらいたったでしょう。
ほほにあたる風は、あまい香りをたっぷりと、かかえこんでいました。気づいた時は、あたり一面 クローバーの緑のじゅうたんでした。
「ねえ、起きてよ。」
と、ひんやりとやわらかいクローバーの葉に起こされて、ようやくまわりがはっきりと見えてきました。
「わたし、ここで何してたのかしら。」
「ししゅうでしょ。あなたの仕事はししゅうでしょ。」
と、クローバーたちは、ささやきました。
「ほら、もっと花をふやして
もっと花をさして
たくさんはちみつとるために
おいしいはちみつとるために」
今度は、もっとたくさんの声が聞こえてきました。
「ああ、わたしは、ししゅうをしているんだった。」
ふと、目をやると、自分のスカートの上に広げたテーブルクロスは、そのままずっと、緑の草原へと続いていました。
その時、一ぴきの大きなハチが、かすみさんに近づいてきました。
「かすみさん、待っていましたよ。わたしは女王バチです。あなたのおかげで、一面 クローバーの草原ができました。これだけの花があれば、わたしたちも生きていくことができます。これからも、ずっとここにいて下さいね。」
たしかに、ハチがしゃべったのでした。
「ずっとここにって?」
「ええ。ここは、ししゅうの国ですから。そのテーブルクロスに、かすみさん、あなたをししゅうするのです。そうすれば、ここでずっとくらせるのですよ。」
かすみさんは、口をポカンとあけたままでした。
「ここはいつも春。永遠の春ですよ。風が気持ちいいでしょう。ほら、立ってごらんなさい。」
女王バチに言われて、かすみさんがふらふら立ち上がると、ミツバチたちがたくさんあらわれて、おいでおいでをするように、かすみさんをさそいました。
一歩ふみだすと、足は軽く、前に進みました。それに、足のうらにあたるやわらかい、クローバーの葉は、なんて気持ちがいいのでしょう。
「まあ、ほんと。体が軽くなったみたい。ひざも、全然痛くないわ!」
そのままどんどん歩いて、小川のそばまで行くと、そっと川の水をすくってみました。
女王バチは言いました。
「春の草原っていいでしょう。ここでは、天気の心配も、年をとる心配もないのです。老眼鏡なんていりませんよ。」
「そうねえ。ここでくらすのも悪くないわね。」
かすみさんは、足が自由に動くことがうれしくてたまりませんでした。草原を歩き回ったり、疲れたらクローバーの上でねむったり子どものようにはしゃぎました。
そして、電話のベルや、車の音にもじゃまされず、すきなだけ、ししゅうをしました。
めずらしい花をみつけたり、木かげで本を読んだりする時間は、何てすてきなんでしょう。静かでおだやかな時間は、ゆっくりとすぎていきました。
それなのに、十日目の夕方になって、ルルと同じ夕焼け空を見た時、かすみさんは急に家に帰りたくなったのです。
「ルルちゃん、どうしているかしら?」
ふと、ルルの声が聞こえた気がしました。
そうぞうしいテレビの音や車の音、向かいのケーキ屋の青いネオンを思い出しました。
それから、雨にうたれて咲くあじさいの花や、木がらしの中でじっと春を待つ、もくれんの木が急に見たくなったのです。
日ごとに、かすみさんはししゅうをしながらため息をつくようになりました。
ししゅう針に当たって、キラキラと反射する春の光が、かすみさんの心をチクチクとさしました。
ある日の夕方、とうとう針を進める手は、パタリと止まりました。
「春ばかりじゃなくていいのよ。」
そう、ポツリと言った時、いつかの女王バチが羽音もさせずに、じっとクローバーの上にとまっていることに気づきました。
「かすみさん、あなたのすがた、ししゅうしなかったのですね。それで、もどりたくなったんでしょう?」
「わたし、気づいたの。冬があるから、春がうれしいのよ。
それに、あのテーブルクロスは、たのまれたものですからね。仕上げて、わたさなくてはならないのよ。」
女王バチは、だまったままでした。
いつの間にか、夕焼け空は、すみれの花のようにそまっていました。
かすみさんは、すみれ色にそまった顔をパッと上げると、
「でも、わたしは、これからもたくさん、花のししゅうをするわ。おいしいみつをとってもらえるようにね。」
そう言って、女王バチを見つめました。
日が落ちて、あたりは急に暗くなりました。いえ、暗いのは、いつものかすみさんの部屋でした。
外は雨がふっているのでしょう。雨のにおいが、かすかにします。
「雨戸をしめなくちゃ。」
そう言って、まどべへ行こうとした時、ひざが、ギクリと痛みました。
「ああ、もどって来たんだ。」
それでもかすみさんは、何だかホッとして雨戸もしめずに、雨の音をいつまでも聞いていました。
時計がゆっくり、八時をうちました。
次の日の朝、テーブルクロスの草原は、ずい分広くなったようです。
「わたし、ししゅうの国でたくさん仕事をしたのね。もうすぐ完成だわ。」
かすみさんは、針を持つと、まどべのいすにこしかけて、仕上げをしました。
そして最後に、
「結婚、おめでとう。」
と、つぶやくと、すみの方に四つ葉のクローバーをししゅうしました。
それから、デパートの店の人に電話をかけたのです。
「紅茶の飲みたくなるテーブルクロス、仕上がりましたよ。きっと気に入っていただけると思いますよ。
それから、次の仕事なんですけど、たんぽぽのカーテンなんてどうでしょう。春のカーテンとして売れませんか?」
受話器を持つかすみさんの声が、いつもより明るくひびいていました。