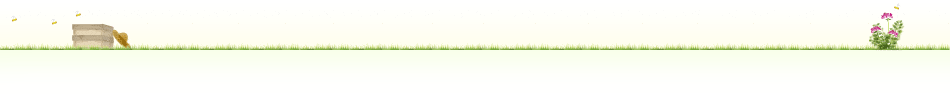健康食品、化粧品、はちみつ・自然食品の山田養蜂場。「ひとりの人の健康」のために大切な自然からの贈り物をお届けいたします。
健康食品、化粧品、はちみつ・自然食品の山田養蜂場。「ひとりの人の健康」のために大切な自然からの贈り物をお届けいたします。
「…というわけやの。しばらくほこりのない所に転校したほうがええと思てねぇ…そやったら美山が一番やろ?」
母親の強引な実家への電話の声がよみがえる。そして、倉子は美山という小さな村に逃げこんだ。小学5年の秋だった。医者である母によると、転地療養というものらしい。わずか1年ほどの期間であったが、倉子はがらりと生れ変わった。何かを考える根っこ、生きる希望と勇気、それに初恋のほろ苦さまで、美山の大自然の中で教えてもらった。あれから15年。倉子は明日から、その美山の診療所で医者として勤務する。美山の星空、澄みきった川、雄大な栃の木、独特の栃蜜、みんな残っているのだろうか、史也君の心にあの頃の美山、あの日の約束は残っているのだろうか……倉子は、次々に浮かぶ思い出をかみしめるように、そっと目を閉じだ。
「最後の頼みの綱なのよ。倉子には美山があっていると信じてる。美山でゆっくり休めば必ず治るわ」
「母さん、何いってんの? 体中がさがさで、血がにじんでいるのに。喉のおくではひゅうひゅう音が聞こえているんだよ。どんな苦いお薬もがまんしたのに。母さんはお医者さんだけど、ちっとも治してくれなかったじゃない。どこに行ってもだめに決まっているよ」
一気にわめくとまた咳がとまらなくなった。吸入器の蒸気のむこうに母さんの泣き顔がぼやけた。だれも私と手をつながない、みんな私がこんこんすると口押さえたり、息をとめたりする。いっしょに遊んでくれる友達なんてひとりもいなかった。九九でさえかゆくて覚えられない。もう死んじゃいたいって思っていた。でも、その言葉は飲み込んだ。その頃の母さんは毎晩、私の喘息発作やアトピーでほとんど寝てなかった。たまに学校に行っても、すぐに熱が出ては母さんが仕方なく迎えに呼ばれた。多分私より落ち込んでいたかもしれない。私は食事制限もあってか、がりがりにやせてあだなはガラ子。にわとりの足みたいだった。本名倉子、だからたいして変わらない。どうせ名前を呼ばれることなんてないんだしどうでもいい。本当に毎日が長くて苦しかった。私、生きてる価値あるんだろうか、でも、何かを考えるとまた全身かきむしるほどかゆくてたまらなくなる。もう私はどうでもよくなっていた。なんの期待もなく、重い頭で何年かぶりに母さんの故郷、美山へと向かったのだ。
美山のばあちゃんは、ずいぶんはでに私の引っ越しを喜んでくれた。
「ようきたねぇ、待ってたんやでー。ひさしゅうみんうちに、大きぃなりはって」
赤黒いかさかさになった首や腕は気にならないのか、私をきつく抱きしめてくれた。自分でも気持ち悪いのにその肌をさすってくれた。しんどかったなぁと何度もつぶやいた。
美山の家はお屋敷と呼ばれていた。山の中腹にあり、門をくぐると庭園があった。家のそばには透き通 った小川があり泳いでいる魚がときおりきらりとする。庭隅には柿の実が重たそうにぶらさがっている。でっかい裏庭には栃の木が、どがんと屋敷全体を包み込むくじゃくの羽のようにそびえ立っていた。家の中はだだっぴろくひんやりと湿っていた。昔の牛小屋を改造した離れ屋もあった。その後ろに蔵もあった。球場ぐらいに広く見えた。
「どの部屋を使うてもええで。いつまでいてもええし寝たいだけ寝て、行きたい時がきたら分校行ってもええ、全部倉ちゃんが好きなようにしはったらええわ」
ばあちゃんは細かく私の世話をしてくれた。うれしくてたまらないと鼻歌まじりに動いていた。村長をしているじいちゃんは、毎日のように村のことで公会堂にでかけてたり、庭木の手入れをしていた。倉子に合うやろ思うてな、と言ってはなんだかんだと買いそろえていた。ピンクの布団におそろいのクッションとカーテンは和風の畳の部屋におそろしくミスマッチだった。絶対喘息によくなさそうなぬ いぐるみもいっぱい用意されていた。退屈しないようにと部屋の全面にびっしりと私が読めそうな本も並べてあった。すべてじいちゃんの見立てだった。今まで自分の存在をこんなに喜ばれていると感じたことのなかった私は、可愛がられるたびにおしりがむずむずした。
美山に早い冬がやってきた。身動きできないほどの雪が毎日積もっていた。ここにきて、私はもう3キロ太った。ばあちゃんのごはんはいままで食べたことのないようなものばかりだった。海の遠い美山は保存食が多い。あれこれ食事に工夫がなされている。なかでも栃餅という木の実を灰でたいてあくをだしてこなにして作ったおやつは私の大好物となった。ばあちゃんといっしょにくるりと丸めて、畑でとれた小豆からはあんこをつくってまぶって食べた。あの堅い木の実がもちっとした感触のおやつになる。どんなこてこてのケーキよりもおいしかった。ほかにも、体にいいと聞けばふたりはあれこれ挑戦してくれた。薬代わりや、とばあちゃんは何かの葉っぱでお茶を作った。湯船にはじいちゃんの発明した薬用ヨモギをいれた。なにが効いたのかわからないが、往診がてら会いにきた母さんは、私を見つめて、絶叫マシンに乗ったみたいに大げさに騒いでいた。確かに、私の体からあのいまいましいかゆみが消えた。喘息の発作もまだ一度もない。横浜ではいつも微熱があったし、一日体がだるかった。美山ではにわとりの鳴き声で目がさめる。井戸水で顔を洗うとしゃきっとする。玄関につもった雪かきを少しだけ手伝えるようになった。でも分校にはまだ行けそうになかった。5年生はみんなで8人という。また嫌われたらと思うと胸の奥がきゅっとなる。子ども同士ってどんな話しをするんだろう、話下手な私には想像さえできなかった。好きな本を読んで、時々ばあちゃんの手伝いをして山のすそからくねくねと流れる川の音を聞いていると、あっというまに夜になっていく。手を伸ばせば届きそうなくっきりとした星空が、栃の木のすぐそばまで降りてきていた。
雪解け水で小川の水かさが急に増えた。その川面にすうっと春の陽射しを感じた昼下がり、男の子を乗せた軽トラックが、ごつごつの一本道を登ってこっちに向かってきた。ここより奥にはもう家はない。
胸が高鳴った。あわてて部屋に逃げ込みカーテンをひいた。2階の窓から、降りてきた男の子をみつからないようにそっと見ていた。
(かっこいいなぁ、誰なんだろう……)
その子のお父さんらしき人が慣れた手つきでトラックから荷物を運び、離れ屋に運んでいく。楽しそうにばあちゃんもじいちゃんも手伝い始めた。男の子はどこ? もう窓からは見えない。ばあちゃんが早く私を呼んでくれることを、わくわくしながら待ったがいっこうに声はかからず、忍び足で下に降りていった。
裏庭に止めた軽トラックにはたくさんの木箱が積んであった。不気味な音と反対に甘い香りがした。なんだろう、近寄ってみたいような怖いような、やっぱり離れ屋をのぞいてみようか、と振り返ったそこに私を見下ろすように男の子が立っていた。
「あんた、だれ?」
私は何も答えられずあわてて母屋にかけ込んだ。そっちこそだれよ、心の中ではちゃんと言えるのに、唇がしばらくふるえていた。
その日の晩、ばあちゃんが言いにくそうに説明をしてくれた。
「春風がふき始めたころにやってきはるんや。6月あたりまでやろかなぁ、うちで宿を用意してあげるんや」
「養蜂家や。ありゃ初めて聞くんかな? 裏の栃の木から栃蜜を集めるんやで。全国でもこんなに上等の蜜が採れる場所はないんやて。うちの木は樹齢何百年やからな」
と、ちょっと誇らしげなじいちゃん。
「トチミツって? 栃の木の蜜?」
「そや、そりゃうまいんや! 倉子も気にいるわ。わしも蜜を採る時は手伝うしな、お礼にたんともろて楽しんでるわ。でも、それだけやないんや、わしは美山の村おこしやと思うとる。全国に栃蜜をひろめたいんや」
「でもなぁ、倉ちゃんがいややったらよそに行ってもろてええんよ、おじいさん、そやろ?」
「そうや、ええんや。でもちょうど倉子と同じくらいの年の子もおるからいっしょに分校に行ってもええと思うてなぁーいややったら無理せんでええけどなぁ……なかなかええ子やし、そやからえーっと」
最後のほうは何を言っているのか聞きとれなかったが、ふたりとも養蜂家の訪問を毎年楽しみにしていたこと、栃蜜が大好きなんだということ、私に気を使ってくれているということもよくわかった。男の子は、2年前に母親が亡くなってからは父子ふたりだけでくるようになったそうだ。蜂蜜を集めて全国を北に移動しているなんて、初めて聞く仕事だった。男の子のこともすごく気になったが、わざとつっけんどんに言った。
「私、いっしょに分校へは行かない。でもあの人たちがいるのは別にかまわないよ。関係ないもん。それに栃蜜には興味あるし」
「そうか、ええか。まっ、学校はまだやな、急ぐことはないしなぁ」
ふたりは顔を見合わせてほっとしていた。