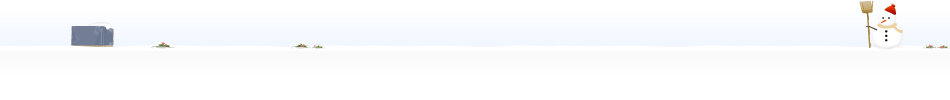健康食品、化粧品、はちみつ・自然食品の山田養蜂場。「ひとりの人の健康」のために大切な自然からの贈り物をお届けいたします。
健康食品、化粧品、はちみつ・自然食品の山田養蜂場。「ひとりの人の健康」のために大切な自然からの贈り物をお届けいたします。
その里におそい春がきて、梅も桃もあんずも、いちどきに花を咲かせました。たんぼの岸には、すみれやたんぽぽや、小さくてかわいい花々が色とりどりに咲いて、あちらこちらに、黄色い菜の花畑や赤紫のれんげ畑も見えます。
おばあさんは、菜の花畑のそばの、白い土塀に囲まれた家に、一人で住んでいました。
子供達は大きくなって遠い町に住み、一緒に暮そうと言ってくれましたが、おばあさんはこの家が好きで、離れたくなかったので一人で暮しているのでした。
次の日曜日には、近くにある観音様のお寺で縁日があります。とくに今年は、何百年に一度というたいへんありがたい縁日にあたるということで、おばあさんも友達とお参りするのを楽しみにしていました。
(そうだわ、何を着ていこうかしら。ぼつぼつ用意しなくては・・・)
水曜日の夜のこと。おばあさんは居間にあるタンスの引き出しを開けて、何枚かの着物を出してみました。
(観音様の長い石段を上るときは、洋服の方が歩きやすくて楽なんだけど、お堂に上がってお祈りしたり、赤い毛氈の上で甘酒をいただく時は、やっぱり着物がいいわねえ・・・気持ちがしゃんと引きしまるから)
おばあさんは着物を仕立てるのが得意で、近所の娘さん達に和裁を教えていたこともありました。
紙に包んでしまっている着物を、一枚ずつていねいに開いてながめていると、色々な思い出が頭の中に浮かび上がってきます。若かったころ・・・だんな様がいて、子供達がいて、とてもにぎやかだったこと・・・
(そういえば今はたった一人・・・静かすぎて、やっぱりさびしいわねえ・・・)
おばあさんは立ち上がって、縁側の障子を開け、サッシ戸の向こうの庭に目をやりました、外はきれいなお月夜でした。子供達と一緒に植えた木蓮の白い花が、月の光を受けてほのかに白く浮かび上がって見えます。
トントントン・・・玄関の戸をたたく小さな音が聞こえました。
(こんな時間に誰かしら・・・)不思議に思って耳をこらすとトントンという音とともに
「こんばんは。夜分にすみません」
どうやら、若い娘さんの声のようです。
「はいはい、いま開けますよ」
おばあさんは急いで玄関に行き、引き戸を開けてあげました。引き戸の向こうに立っていたのは、どこかの工場の作業服のような、黄色い上着と黒っぽいズボン姿の、若い娘さんでした。見覚えのない人でしたが、色白できれいな目をした、美しい娘さんです。
娘さんは、風呂敷に包んだものを玄関の床におき、自分は立ったまま、おばあさんに向かって深く頭を下げてから言いました。
「勝手なお願いですが、この反物でわたしの着物と帯を仕立てて下さいませんか。どうしても、土曜日の夜までに欲しいのです。おばあさまのほかには、お願い出来る人がいません。どうかおたすけ下さい。」
おばあさんは驚きました。
「私はもう長いこと、人様のものは縫ってないんですよ。町へ行けば、若くて腕の良い和裁士さんがおられると思うけど・・・」
娘さんは首を横にふって云いました。
「いいえ、それはだめなんです。私、昼間は工場で働いているので町には行けません」
「そうなの・・・困ったわねぇ」
土曜日までにはあと三日あります。若い時には、上等の着物一枚、夜なべして一日で縫い上げたこともあるおばあさんですが、今では目も悪くなり、すぐに疲れるので、とてもそんなに早くは出来ません。三日というのは、おばあさんが着物と帯を縫い上げるのに、やっとなんとか・・・という期間でした。
おばあさんは、お金に困っているわけでもないので、無理して疲れる仕事をしたくはなかったのですが、娘さんから一生懸命にたのまれると、断るのも気の毒に思いました。
「それでは、とにかく反物を見せてもらいましょう。どうぞお上がりくださいな」
娘さんを居間に案内して、おばあさんは娘さんの持ってきた反物をのばして見ました。
「これはまぁ、なんときれいだこと・・・」
反物には、菜の花のような明るい黄色地に、赤紫と白の藤の花のしだれ咲く様子が、それはそれは美しく描かれていました。
「・・・この反物と帯地は、両親の形見です」
娘さんは、小さな声で言いました。
「形見?ではご両親とも、お亡くなりになったのですか」
「はい、ずっと以前に・・・」
うなずいた娘さんの目が、少しうるんでいるように、おばあさんには見えました。
「そうですか。他に頼む所がないのなら、なんとか私が縫ってみましょう」
おばあさんが言うと、娘さんは嬉しそうに目を輝かせ、畳に両手をついて丁寧にお礼を言いました。
(いまどきの娘さんにしては、珍しいくらいお行儀が良い人だわ。それにしても、この香りは何かしら・・・)
おばあさんが不思議におもったのは、娘さんが立ったり座ったり動くたびに、ほのかに漂う匂いでした。良い匂いではあるのですが、香水の匂いとは少し違うようです。
「工場へお勤めだそうだけど、工場ではどんなものを作ってらっしゃるの」
おばあさんがたずねると、娘さんは少しの間考えてから、
「体に良い食物とか、お薬とか、それに化粧品も作っています」
と、答えました。
「そうですか。それで、なんだかお花畑にでもいるような、良い匂いがするのね」
「あら、私は全然気がつかなくて・・・」
娘さんは、なぜかあわてたような、困ったような顔をしてうつむきました。その様子が何かとても辛そうにみえたので、おばあさんは工場の名前も場所も、それどころか娘さんの名前さえ聞きそびれてしまったのでした。
娘さんは、おばあさんに幾度もお礼を言って、月明かりの道を帰っていきました。
(あの人がどこの誰であっても、この着物と帯だけはきちんと仕立ててあげよう・・・)と、おばあさんは心に決めました。始めて出会った人なのに、なぜか遠い昔を思い出すような、不思議な懐かしさを感じて、おばあさんは久しぶりに縫物へのやる気が出てきました。
次の日も、その次の日も、おばあさんは娘さんの仕立物のためにせいをだしました。でも、おばあさんは年をとっているので、あまり長い時間頑張り続けることは出来ません。
金曜日の午後は、とてもうららかなお天気でした。縁側の座布団に座って、縫い物を続けていると、思わずうとうと・・・居眠りしそうになりました。そこで外の風でも入れようとサッシ戸を開けると、春風にのって色々な花の香りが流れこみ、一匹の蜜蜂が、小さな羽音をたてながら飛んできました。
おばあさんは羽音を聞いた時、刺されると恐い大きな蜂ではないかと思って逃げ出す用意をしましたが、よく見ると、小さな蜜蜂だったので、そのまま仕事を続けました。
蜜蜂は、ほとんど出来上がった娘さんの着物の上を、ゆっくりと飛んでまわりました。
(おやまあ、この着物に描かれた藤の花があんまり綺麗なので、蜜蜂も気にいって離れにくいのかしら・・・)
おばあさんは蜜蜂にむかって呟きました。
「綺麗でしょう?でもこの藤の花から蜜は取れないわ。これはある娘さんの、大切な着物だから、汚さないであげてね」
おばあさんの言うことがわかったのかどうか、蜜蜂は静かに庭の方へ去っていきました。
そして土曜日の夜には、あの娘さんの着物と帯はしっかりと見事に縫い上がりました。
おばあさんは、自分の衣紋掛けに、出来あがった着物をかけて娘さんを待ちました。
(きっと喜んでくれるわ・・・)
おばあさんは、娘さんに着せかけてあげるのを楽しみに、座りなれた座布団に座って、ガラス戸の外の夜の庭をながめていました。
その夜もきれいなお月夜でした。満月にちかい大きな月が、春のかすみにうっすらと包まれた、きれいなおぼろ月の夜でした。
「おばあさま・・・おばあさま・・・」
いつのまに、うとうと眠ってしまったのでしょうか。おばあさんは娘さんの声で目をさましました。
「あらまあ!あなたは・・・」
おばあさんはとても驚きました。部屋の片隅に、あの娘さんが座っていました。それだけならそんなに驚かないのですが、娘さんは縫い上げた着物を着て、帯もしっかりと結んでいるのでした。その姿は、何かの時代劇から抜けだしてきた姫君のような、とても美しいものでした。
「着物と帯、きれいに縫い上げて下さって、本当に有難うございました。このご恩は、決して忘れはいたしません。けれどじつは私・・・人間ではなかったのです。いまやっと、観音様のお救けをいただいて、五百年前の私の姿に戻らせていただきました・・・」
娘さんの話は、とてもとても不思議なものでした。