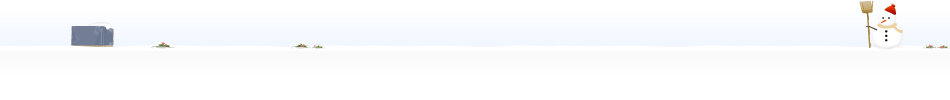健康食品、化粧品、はちみつ・自然食品の山田養蜂場。「ひとりの人の健康」のために大切な自然からの贈り物をお届けいたします。
健康食品、化粧品、はちみつ・自然食品の山田養蜂場。「ひとりの人の健康」のために大切な自然からの贈り物をお届けいたします。
「若様、お勉強中失礼します。」
家老が急用とばかりに飛び込んできた。私は、ちんぷんかんぷんの蘭語の勉学をしているとみせかけて、 城内の者たちにナンバン風の挨拶を教えてあげていたところであった。
城主の私は今年で二十と四だが、いまだに奥方がいない。爺は私が真面目に勉学に励まないせいだという。 それで、読み書きをおろそかにすると爺がうるさいのだが、勉強よりも皆の相手をしていた方がずっと面白い。
「お、爺か。私は今、勉学に忙しいのだ。面倒くさいことは聞かんぞ。」
「は。民衆が申すには、近頃毎晩のように真っ黒な大入道が蔵という蔵の蜂蜜をなめ尽くしてしまうため、年貢が納められないと…」
私は町のみんなに蜜商業の義務をかせており、大量の蜂蜜を年貢にとっている。理由は私が大の甘党であるから、それだけである。 私の楽しみといえば、皆でわいわい騒ぐことと蜜を食うこと、このふたつなのだ。
「なあに、そいつは冬ごもり前の熊だ。すぐ撃ち殺せばすむことではないか。」
「いいえ、若様。町の衆は、これは蜂蜜なめなめ妖怪の仕業と申しておりまして…」
「蜂蜜なめなめ妖怪!はん。町民どもめ、嘘を申すならもっとましな嘘を申すがよい。こりゃあ年貢逃れの作り話だ。 だいたい私のものになるはずの蜂蜜をそんなわけのわからん妖怪なんぞに簡単に横取りされてたまるか。 爺はその妖怪がまことにいると思うのか。」
「わたくしはそんなこと一言も申しておりません。若様ご自分でご確認なさったら…」
「馬鹿を言え!私は忙しいから駄目だ。」
私は時代に先駆けて、外交に力を入れる新時代の殿様になるため日々勉学に精進しなくてはならないのだ。そう申したら爺が、
「それならば家臣たちのお相手をなさる時間もございませんね。」
などと生意気な口を利くから、私はいずれナンバン娘を奥方に迎えるつもりだからナンバン人のおもてなしも練習しておく必要があるのだと返してやった。 そして、こう言いつけた。
「立て札を!妖怪をしょっ引いてきた者には賞金をやる、と。」
翌朝、爺が私のところに飛んできた。
「若様。皆、賞金よりも自分の命が大事だと申し捕まえたがりません。」
「む、なんという臆病者どもだ!」
「なにしろ、ものすごい図体の妖怪だそうで、身の丈が八尺三寸の大入道だと。」
「八尺!信用ならんな。捕まえてこられぬところをみるとやはり作り話なのであろう。」
「それではらちがあきません。やはりご自分でお確かめになられたらよろしいのでは。」
「よおし分かった。あす、私が行く。」
面倒なことになった。私が行くからには何としても捕まえなければ城主として体裁が悪い。 それにしても、そんな馬鹿げた妖怪など本当に存在するのだろうか。もし本当にいて八尺もあり、 取り逃がしてしまったら…私の信用がなくなるばかりか、ますます婚期を逃すことになるに相違ない。 それだけはまずい。どうしたものか。
考えた末、名案が浮かんだ。今晩早く床に就くふりをして、前に柄が気に入ったので献上させた家臣のぼろきれをまとい、 浪人になりすましてこっそり城を抜け出し下見をしておこうというものだ。
戌の刻すぎ、早速臭いぼろを羽織り、髪をばさばさ適当に結い直すと、なんだか本物の浪人のような心持ちになった。 抜け出すのは簡単だった。というより今宵抜け出してみて初めて、我が城の警備の甘さを痛感した。
蜂蜜倉は南大路をつきあたり、角の茶屋から三十間先の柳の揺れる太鼓橋を越えたところにある。 下町へ出るのは先月、お忍びで爺と浴衣祭に出向いて以来だ。あの時はおびただしい人波に呑まれ死ぬ思いだったが 今日は実に閑散としている。人っ子一人見当たらない。夜中というせいもあるが、かっちり閉まった雨戸がえらい緊迫感を 漂わせていた。私もそんな雰囲気に圧されてか、蜂蜜蔵のほうへ一歩近づくたびに鼓動が高鳴り始めた。 億劫というより怖くなってきた。夜風は冷たく太鼓橋を越える勇気を凍えさせた。
「さっきの茶屋で茶でもすすって、気持ちを落ち着けることにしよう。」
私はさっき通った蜂蜜茶屋をたたき起こして、そこで一服することにした。浪人なら誰でもそうするように、 嫌がる女将に懐の短刀をくらわすぞ、と脅かしてどうにか店を開けさせた。我ながら姑息な手口を思いついたもんだ。 軒先に腰掛けて蜜団子と抹茶を頼むと、後から、こんな時刻に団子がいただけるとはありがたい、と御用人がやってきた。 そしてあっしにも同じものを、と言って私の隣に腰を下ろした。歳は私と同じ頃だろうか。じろじろ眺めていたら声をかけられた。
「お、こりゃ新顔ですね。旦那も賞金稼ぎですかい?あっしもそのくちでね。今宵で三日目の挑戦なんですが、 妙にすばしっこい奴で三度とも取り逃がしちまいましたよ。」
御用人は、はははと笑い、店の女将が持ってきた茶をすすった。
「三度も捕まえようとしたのか。」
「ええ。けど、とにかく大っきくって。目ん玉は青白く光るし。一度声も聞きやしたが、とても人間の声とは思えませんでしたよ。 仲間はみんな怖気づいちまいましてね。」
男の話は面白いとは思ったが、やはり信じる気にはなれなかった。
「みんな怖がっているというのに、お主は怖くはないのか?」
「あっしは怖がってもいられねんでさ。」
そう言って御用人は紺青の闇に染まる城のたつ山の方を指差した。
「あの山の裾野の方に、養蜂場の隣接する蜂飼い村という小さな村がありまさあね。 蜂蜜商の使用人などは、あの村からとれたての蜂蜜をたっぷりつめた樽をかついで、えっさほいさとここの蔵まで運んでくるわけですが…」
村はここから三里も遠くだというから、たいそうな仕事もあったもんだ。
御用人はあの村に母を残してきたという。母上の働く養蜂場のためにも、あのいまいましい妖怪をやっつけて景気を よくしたいのだそうだ。ただの賞金稼ぎとはわけが違う。私は彼の勇気をうらやましく思った。
「しかし、ここの上様ときたら。」
「え、私!」
「あんたじゃねえ、上様と言ったんでさ。あんなに年貢を納めさせて、町の者や村の者がどれほど困っているか少しは考えて もらいてえよ。なあ、旦那。あんただって金に困ってっから賞金稼ぎに来てんでしょう?」
「え、ええ、まあ。」
私は恥ずかしくなった。うつむいて残りの茶を飲み込んでしまい、気まずいのでそそくさとこの場を離れようとしたら、 茶屋の婆さんに袂をつかまれた。お代がまだだというのである。私は大いに弱ってしまった。いつも爺に任せきりであったから、 うっかりして金を一銭も持ち合わせてこなかったのだ。
「あす、爺に届けさせよう。」
「何を偉そうな、お殿様じゃあるまいに!」
「旦那、ここはあっしが。」
かたじけない、と私は御用人に頭を下げた。御用人に頭を下げたのは初めてだ。彼は愚痴を聞いていただいたお礼ですよ、と笑った。 なんとも気持ちのよい男だ。このような男にはいくらでも頭を下げてやりたくなる。
さて、そのときだ。蔵のある方角から誰ぞの叫び声が闇夜を切り裂いた。御用人は出たなと一声もらすと、 よしと意気込んで大蔵へと走り出した。勢いに押されて私も彼の後を追っかけた。息を切らせて橋を越えたとき、 私たちの目に飛び込んできたのは確かに八尺ありそうな大入道の姿だった。黒装束をひるがえし、すさまじい速度で蔵を後に するその妖怪を、御用人は慌てて追っていったがあの速度では到底追っつけまい。私は当然、追いかける振りして逃げ出していた。 あんな妖怪にとって食われてはたまらないものな。まさか、まことにおるとは思わなかったが、とにかくあすは、 何か言い訳でもして妖怪退治はごめんこうむることにするのだ。
私は路地を抜け河原の方面まで走った。すると厄介千万見知らぬ通りに出てしまった。 表通りとは一変してこの界隈はどの屋敷からも行灯の光とにぎやかな笑い声がこぼれ出ている。旨そうな匂いもする。 ここは、旨いものには目がない私のためにあるような料亭横丁だったのだ。一軒の料亭をのぞいていたら、 一人の若い仲居が声をかけてきた。
「おや、旦那ってば疲れた顔しちゃって。あがって休んで行きなさいな。美味い蜂蜜酒でもごちそうしてやるよ。ほら、入った入った。」
仲居は力任せに私の腕をぐいとひいて、お座敷へ招き入れた。彼女は「ひろ」といった。この女のよくしゃべること!
「旦那お仕事は何なさってんだい?やっぱり蜜屋?それとも養蜂かい?もし蜂蜜に余りがあったらあたいに少し分けておくれよ。 近頃、妖怪騒動で蜂蜜が値上がりしちまって、とてもあたいのお給料じゃあ手が届かなくてね。ねえ、旦那はどこの蜜屋なの?」
「わた、おれは…流れ者さ。」
私はとっさに嘘を言った。
「この町に働きに来たってことかい?ねえ、そんならお故郷はどこなんだい?」
「あっち、いやむこうの方。」
私はお城のそびえる山を指し、そのむこうだと言った。
「おや本当かい?じゃあ蜂飼い村の方だね。あたいもあの村の出なんだ。同郷のものに会えるなんて思ってもみなかったけど 嬉しいもんだね。おや旦那、お酒が進まないじゃないか。お口に合わなかったかい?」
「おれは…その、下戸なんだ。」
「まあ嫌だ。そんならもっと早くお言いよ。代わりに何か…あ、そうだ。」
ひろは何か思いついた様子で袂に手を突っ込んだ。
「同郷の好だもんね。一さじごちそうするよ。」
取り出したのは赤い茶巾に入った小さなつぼだった。
「今となっては貴重品だよ。ひいきにしてもらってる蜜屋に無理言ってもらったんだ。たった一さじでも口に入れれば 疲れなんて吹っ飛んじまうよ。なんせこの一さじは赤子蜂のために姉御の蜂が命をかけて集めた蜜の一生分なんだもの。」
そんなこと、これまで考えたこともなかった。ひろは、さじいっぱいにのせた蜜をぼんぼりの明かりにきらめかせながら 私の口もとへ運んだ。蜜が口の中でほどけて広がる。
「ん、…美味い!」
これまで口にしてきたものとは比べ物にならない。格別に美味かった。
「ほうら、疲れてるのなんか忘れちまうだろう?」
「お前もこいつをなめてるおかげでそんなに元気がよいのだな。」
「あはは、あたいが元気なのはもとからだよ。この蜂蜜はお故郷への土産なのさ。 おかしな話だけど、村の者は自分とこでとれた蜜を滅多に口にできないんだ。みんな年貢にもってかれちまうからね。 封を切ったのはあんたが疲れてる顔してたからよ。同郷の者と聞いてじいちゃんを思い出したんだ。 お父が戦で死んでね、おととしお母も病気で死んじまってさ。 じいちゃんは今、一人で養蜂の下働きしてちっちゃい弟や妹を育ててくれてるの。 あたいがこっちで稼げるようになったから、少しは楽になったかと思ってたのに、この妖怪騒ぎで客足が減っちまってさ。 今年の暮れには土産物たくさん抱えて帰ろうと思ってたけど、この調子じゃ餅も買えないわ。」
「ひろはいくつなんだ。」
「あたい?あたいは十五よ。」
「十五で出稼ぎか。辛かろうに。」
「そりゃあ…そういうこともあるさ。」
ひろは八重歯で唇をかみ、顔を背けた。その瞬間、横顔に十五の少女の本音がちらりと見えた気がした。 可愛い。私の視線は彼女に釘付けだった。
「でもあたいは蜜蜂なのよ。故郷を出る前じいちゃんから聞いたの。働き蜂はみんな女子なんだって。 赤子のために命がけで一生働いて、もし敵が攻めてきたら戦をするのも女子の蜂が力を合わせるんだって。 それを聞いてね…あたいは、ここで蜜蜂になったつもりで働こうって決めたんだ。」
「先ほどの蜂蜜はお前の気持ちそのものだったのか。大事な土産物であったのに封を切らせてしまって悪かったね、ひろ。」
「いいんだよ。悪いのはお殿さんだもの。」
「え、私!」
「旦那じゃない、お殿さんだよ。年貢の取立て高があんまり厳しすぎるのさ。 取り立てたあげく、みんな一人でたいらげちまうって言うんだから呆れた人だね。おまけにおかしな妖怪まで出てきちまってさ。」
私は愚か者であった。私がこの情けない殿であることがひろにバレてしまったら…。 私はひろには嫌われたくなかった。ここは一つ年貢を取りやめ、あの妖怪を退治し汚名返上といきたいところだ。 格好のいいところをみせればひろの賞賛を独り占めできる…そう思うと、がぜん妖怪を退治する気がおきた。 そのとき、妖怪に怖がってもいられない、という御用人の言葉が私の脳裏をよぎった。
「ひろ、心配はいらん。本日限りで年貢制度は廃止だ。おれが馬鹿な殿にきつく申し立ててやる。 あんたのせいで町や村の衆がどれほど困っているか、とな。それから妖怪も一刻も早く退治するように話をつけよう。」
「本当かい!そうか、分かった。旦那はお城で働いているお役人さんなんだね。旦那と会えたのも何かの縁ね。 今夜のお代はとらないから、その件どうか頼んだよ。」
ひろは行灯の灯を瞳に浮かべて元気に言った。まかせておけ、と私は請合った。