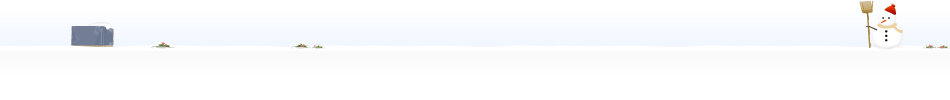健康食品、化粧品、はちみつ・自然食品の山田養蜂場。「ひとりの人の健康」のために大切な自然からの贈り物をお届けいたします。
健康食品、化粧品、はちみつ・自然食品の山田養蜂場。「ひとりの人の健康」のために大切な自然からの贈り物をお届けいたします。
木の洞に似たお店の真ん中に、まり子は立っていました。カウンターに座っていた女主人が、ゆっくりとふりかえります。
「幸江は泣き虫で、怖がりだったわ。小さい頃なんて毎日泣いてばかり、逃げることしかしらなかった」
「まさか……」
まり子が知っているおばあさんは、いつも笑っていました。太陽が明るいのは当たり前のことのように、おばあさんがいつでも強く明るいのは、まり子にとって、 当たり前のことだったのです。
女主人は、くすりと笑いました。
「年の離れた近所の男の子が、ある日、はちみつ石けんを渡してこう言ったの。これは勇気の石けん。これで顔を洗ったら、もう泣いたりしない。どんな時もまっすぐに顔をあげて歩いていけるよって」
女主人はカウンターに置いたままの写真盾に、優しい眼差しを向けました。
「それから幸江は変わったの。泣きそうになるとぐっと唇を引き結んで、怖がりながらも壁にぶつかっていく子どもになった。びっくりするほどきれいになって、どんどん広い世界に飛び出して行って、歌劇団のスターにまでなったわ。でもそんなきらびやかな世界も、あっさり捨てて、今にもつぶれそうな養蜂場に戻って来た。誰もが終わりだと思っていたのに、幸江は黄金のみつを取り戻した。はちみつ石けんをくれた初恋の人と結婚して、養蜂場はどんどん大きくなったわ。でも、あの戦争があって、 夫と生まれたばかりの男の子を亡くした幸江は、一度は私たちの仲間になったの」
まり子と同じように、ミツバチのエプロンを身にまとい、この暖かく心地良い世界で黄金の蜜を運び続けたのでしょう。
「そして七年たった時、幸江はエプロンを外して……ここから出ていった」
「裏切られたと、思った?」
「そうね、少しは」
女主人は、ほっと息をはきました。
「でも、それ以上に誇らしかった。あの時の幸江のきれいだったこと」
まり子は気がつきました。ああ、何年も何十年も、おばあさんに石けんを贈りつづけてくれたのは、この人だったのだと。
「幸福になって欲しいと、いつでも思っていたわ」
まり子は、ぎゅっと唇をかみました。そうしないと、泣いてしまいそうだったのです。もしも泣いたら涙はきっと、はちみつ色をしているだろうと、まり子は思いました。きらきらと、光あふれる金色の涙。
「さあ、もうお行きなさい」
さらりと、衣擦れの音を立てて、女主人が立ちあがりました。
「あなたはあなたの場所に。……私たちも戻りましょう」
白い手が、さっとふられ、それが合図でした。ざあっと波に似た音とともに、世界がくもります。吹きぬけた強い風に、まり子は思わず顔をおおってしゃがみこみました。
そして、草の匂いに目をあければ、まり子が立っているのは、夕暮れの野原だったのです。はちみつ屋の看板が揺れる小さな店はなく、一本の木がそこにありました。
立ちあがり近づくと、朽ちかけた木には大きな洞があり、からっぽになった、はちの巣だけが残されていました。本当にかすかな、はちみつの香りとともに。